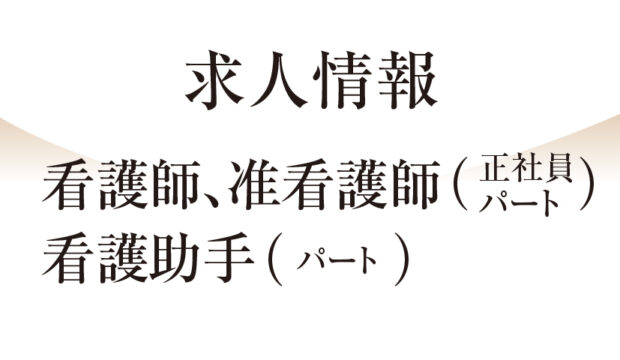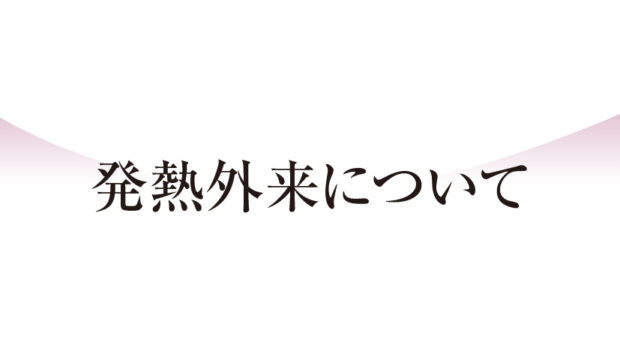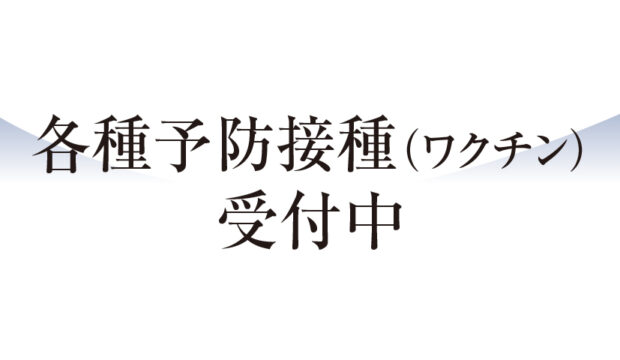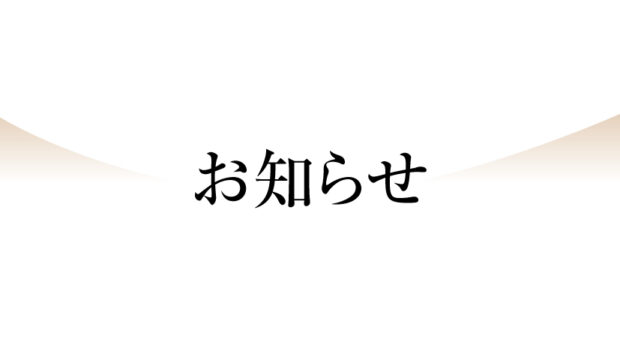血便・下血とは

血便は、血液が混入した便です。肉眼で明らかなものと、そうでないものがあります。鮮明な赤色の血便は通常、肛門近くからの出血を示し、黒色の便は食道、胃、または十二指腸からの出血のサインとなります。これは、血液が胃酸と反応するか、時間が経過することによって色が変わるためです。
便潜血検査は健康診断で行われており、肉眼では見えない微量の血液が便に含まれているかを検出します。
この検査は大腸がんや大腸ポリープの早期発見に役立つ可能性がありますが、陽性結果が出た場合でも、出血の原因は他にあることが多いです。そのため、確定診断のためには大腸カメラ検査が必要になります。
血便が出る病気と症状について
肉眼で見える血便は、様々な消化器系の病気の兆候になります。出血源は口腔から肛門に至る、消化管のどこかであると疑われますが、血便の色の特徴から出血箇所を特定する手がかりを得ることができます。
これにより、考えられる疾患を特定することが可能です。
血便の色とそれに関連する病気及び症状は、以下の表に示されています。さらに、肉眼では確認できない微量の血液が便に混じっているかどうかを検査する便潜血試験が陽性である場合、その多くは痔からの出血によるものです。
実際に、陽性と判定されたのを機に精密検査を受けた方の30~40%には、大腸ポリープが見つかりました。大腸がんが見つかる確率は約3~4%とされています。
血便・下血の種類
血便・下血は、便の状態や色によって、出血している場所や疾患を、ある程度判断することができます。
【鮮血便】
見た目は鮮やかな赤い血便です。痔、直腸がん、直腸ポリープなどが原因で、出血箇所が肛門付近から起こることで発生します。
出血の量が多い場合は、感染性腸炎や大腸憩室出血、虚血性腸炎などの大腸疾患も疑われます。
【暗赤色便】
黒っぽいくすんだ赤いレンガ色をした血便です。大腸がん、大腸ポリープ、大腸憩室出血、虚血性大腸炎、感染性腸炎、潰瘍性大腸炎、クローン病、小腸潰瘍などが原因で、大腸に近い小腸からの出血が考えられます。
【黒色便(タール便)】
真っ黒いタールのような見た目の血便です。上腹部からの出血が原因で、血液が胃酸と混じることで酸化して黒っぽくなります。黒色便の原因を調べるためには、胃カメラ検査を行う必要があります。
胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がん、胃食道静脈瘤、小腸潰瘍などの疾患が疑われます。(貧血で鉄を内服している方は、副作用として便が黒くなることがあります。)
【粘血便】
粘り気のあるいちごジャムのような血液が便に混じっている状態です。
潰瘍性大腸炎やクローン病、アメーバ腸炎などの疾患が疑われます。
血便・下血の検査方法
血便・下血が起こる原因疾患は様々です。そのため、便の状態は発症した時期、腹痛の有無、排便頻度などを診察で伺い、必要と判断された場合には血液検査や胃カメラ、大腸カメラ検査を行って、原因を調べていきます。 当院では、鎮静剤を使用して苦痛を抑えて楽に受けられる胃カメラ・大腸カメラ検査を行っています。土曜・日曜も内視鏡検査に対応しているので、平日に検査を受けることが難しい方も安心して検査が受けられます。胃カメラ・大腸カメラの同日検査にも対応しておりますので、血便・下血の症状が出た方は早めにご相談ください。
血便・下血の治療方法
原因となる病気が多数ありますので、感染性か非感染性かなどを判断するため、症状や食事内容、既往症と服薬などについてくわしくお話をうかがって、必要と思われる検査を行います。血液検査や便検査のほか、出血源を調べる検査などがあります。便の検査は結果が出るまでに数日かかるため、激しい下痢などを伴っている場合などには、対症療法を行って脱水や症状を緩和させることも重要です。
出血源がどこにあるのかを調べるためには、まず直腸指診を行います。肛門や直腸に問題がある場合、これでほとんどが発見できます。
次に内視鏡検査で、腸粘膜の状態を直接観察して、出血源を探し、病変の状態を確認します。内視鏡検査では、病変の組織を採取して生検を行うことも可能です。
こうして出血源や病変を確認し、それに合わせた治療を行っていきます。
血便の予防
血便の原因である大腸がんを予防する最良の方法は、無症状のうちに大腸カメラ検査をこまめに受けることです。多くの大腸がんは良性のポリープから発生するため、早期発見し検査時に切除していけば、がん化を防ぐことができます。
日常生活の中での予防策としては、定期的な運動が有効とされています。
激しい運動は必要ありませんが、運動を習慣化することをお勧めします。
さらに、食物繊維の摂取も予防に有効であり、最近の研究ではその効果が認められています。また、低糖質の野菜、ビタミンD、牛乳、カルシウム、果物、魚なども予防に役立つとされています。
薬剤に関しては、非ステロイド性抗炎症薬やホルモン補充療法がリスクを下げるのに有効とされていますが、副作用のリスクもあるため、医師の指示に従って慎重に使用する必要があります。無闇に服用することは避けるべきです。