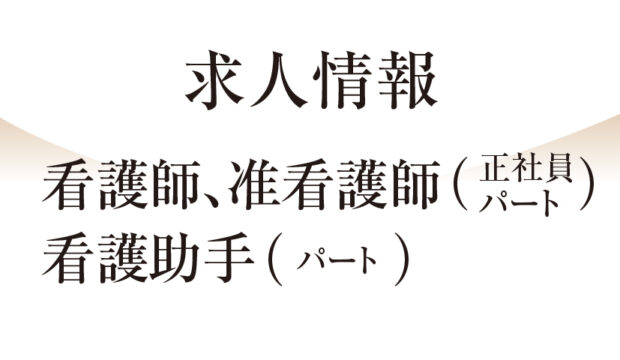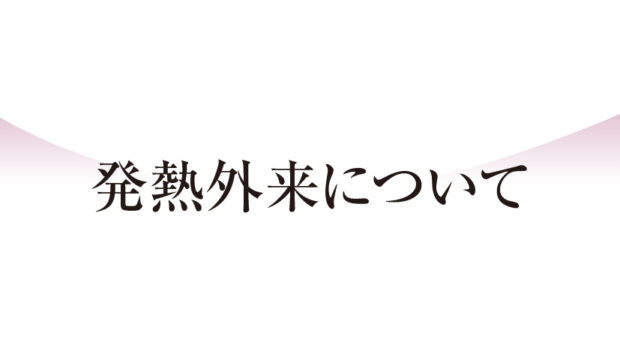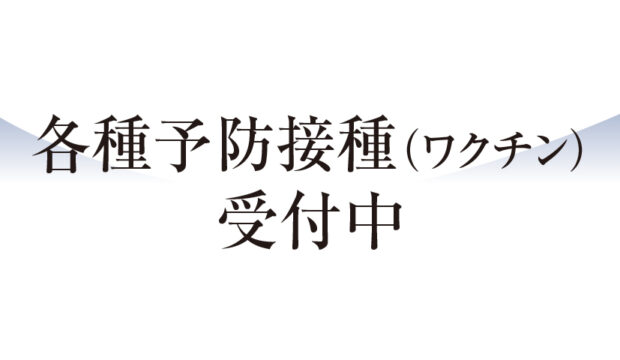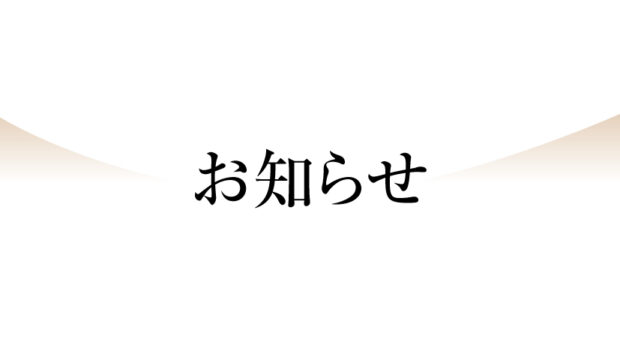胃痛・胃もたれ
【症状は?】
① 胃痛とは?
胃痛も腹痛の一種です。腹痛の中でも胃痛は、食道下部から胃・十二指腸までに何かがおこっているときの痛みです。消化管はあまり痛覚神経をもたず、粘膜側に物理的な刺激を与えてもほとんど痛みを感じることはありません。ところが、消化管の周りの神経の構造によって、収縮したり拡張したり捻れたりといった刺激には、非常に強い痛みを感じるようにできています。また、消化管内部で言えば、健康な胃は胃酸に対して痛みを感じることはありませんが、粘膜に炎症を生じると痛みに敏感になり、胃酸がでると胃痛がおこることになります。つまり、胃が痛む場合は、何らかの理由で胃が痙攣をして収縮している状態、ガスなどが溜まりすぎて胃が拡張している状態、食道下部から十二指腸までに炎症がおこっている状態が考えられます。 いずれの場合でも、治療に緊急を要するケースがあるような疾患のサインとなっていることが多く、お早めに消化器内科などに相談してください。
② 胃もたれとは?
胃もたれは、食べ物の消化がスムーズにいかないことで起きる症状です。誰もが一度は経験する症状なので、胃もたれが起きても受診まで考えるかたは少ないかもしれません。しかし、慢性化した胃もたれには胃潰瘍や胃がんなどが隠れているケースもあります。症状が長引く場合は早期受診が必要です。
一時的な胃もたれは誰にでもあることですが、その他にもストレスや、過労によって自律神経が乱れると、胃から腸へと食物を移動させるぜん動運動が上手く働かなくなって胃もたれがおこることがあります。さらに加齢、女性ホルモンの影響などの他、ピロリ菌感染やその他の疾患などで慢性的に胃もたれがおこっていることもあります。続く胃もたれにお悩みの方は、いつでもご相談ください。
【原因は?】
胃痛や胃もたれの原因は多岐にわたります。まずは内視鏡検査(胃カメラ)を受けて、胃や十二指腸に異常があるかどうかを見ることが診断への大切なプロセスとなります。 時として、胃の裏側にある膵臓の炎症や腫瘍が原因となっている場合もありますので、腹部超音波、血液検査などの検査も必要に応じて行います。
① 機能性ディスペプシア(FD:functional dyspepsia)
機能性ディスペプシアとは、胃カメラ検査などを行っても器質的な問題が見つからないにもかかわらず、胃の痛み、胃もたれ、胸焼け、吐き気、胃のむかむか、ゲップ、胃の灼熱感、早期飽満感などの症状が見られる病気です。
機能性ディスペプシアは、比較的新しい概念です。以前は「ストレス性胃炎」に分類されていました。
ストレス、暴飲暴食、不規則な生活、ピロリ菌感染、喫煙などが原因として挙げられます。
② 胃・十二指腸潰瘍
胃潰瘍・十二指腸潰瘍は、胃や十二指腸の粘膜が深くえぐれてしまう病気です。本来であれば胃液で粘膜が大きく傷つくことはありませんが、何らかの原因によって、胃液が粘膜を溶かしてしまうのです。
胃やみぞおちの痛み、胸焼け、吐き気などの症状を伴います。また重症化した場合には、吐血やタール便(黒い便)といった症状も現れます。。
胃潰瘍は70代以降、十二指腸潰瘍は60代以降でよく見られますが、現在のストレス社会においては、若い人が発症することも多くあります。
③ 急性胃炎
急性胃炎は、特定の原因が起こってから短期間にうちに起こる胃炎で、胃炎とは、胃の粘膜が赤くなり、腫れやただれを起こす状態です。
胃は食べ物を一時的に保存し、消化や殺菌を行う器官です。この機能を正常に行うには胃液が必要になります。胃液には強い酸性を示す胃酸と、消化酵素のペプシンが含まれ、食べ物を分解します。
胃液は非常に強力な酸性を持ち、理論上は胃壁を溶かすこともあり得ますが、胃粘膜は粘液によって保護されています。通常、胃液の攻撃因子と粘液の防御因子のバランスが保たれ、胃粘膜は損傷を受けません。
しかし、何らかの原因でこのバランスが崩れると、胃粘膜が胃酸によってダメージを受け、炎症が生じると考えられています。
④ 慢性胃炎
慢性胃炎は、胃の粘膜に長期にわたる炎症が見られる状態を指します。この状態では、特定の病気がなくても胃の違和感や吐き気といった症状が現れることがあります。
炎症は、赤みや腫れ、ただれといった形で現れ、これらは検査によって確認されることもあれば、患者様の訴える症状や他の原因に基づいて慢性胃炎と診断されることもあります。
慢性胃炎が長く続くと、胃液の分泌を担う胃腺が減少し、胃粘膜が薄くなり、萎縮してしまうことがあります。これを「萎縮性胃炎」と呼びます。
萎縮性胃炎は、胃がん患者においてよく見られる胃の状態ですが、必ずしも胃がんへと進行するわけではありません。
⑤ 胃がん
胃がんは、食べ物を消化する器官である「胃」の壁にできる悪性腫瘍です。初期段階では自覚症状が乏しいため、気づかないうちに進行してしまうケースも少なくありません。そのため、定期的な検査が非常に重要になります。 当クリニックでは胃カメラ検査(胃内視鏡検査)をはじめ、最新の検査機器と経験豊富な医師による精密な診断で、胃がんの早期発見に努めています。
【治療は?】
① 機能性ディスペプシア
機能性ディスペプシアの症状や現れ方には個人差が大きいため、治療も各患者様の状態に合わせて柔軟に対応していく必要があります。
治療の基本方針としては、生活習慣の見直しやストレスへの対処などを含む生活指導と、胃の働きを整えるための薬物療法を組み合わせて行うことが一般的です。
● 薬物療法
薬物療法では、症状の内容に応じて薬剤を使い分けていきます。胃酸分泌抑制剤、胃の働きを活発にするお薬、あるいは胃の緊張を和らげるお薬などが主に用いられます。
● 生活習慣や食生活の改善
自律神経の乱れは、胃腸の働きに大きく影響を与えます。まずは、自律神経のバランスを整えるために、規則正しい生活リズムを意識することが大切です。 水分はこまめに補給し、食事は少量ずつゆっくり摂るようにしましょう。食べ過ぎには注意し、消化を妨げないよう食後すぐの運動は避けることをお勧めします。
② 胃・十二指腸潰瘍
胃酸の分泌を減らす薬や粘膜保護薬を用いて症状を軽減します。ピロリ菌に感染している場合は除菌治療を行います。
痛み止めの薬(非ステロイド性抗炎症薬)などによって起きた薬剤性の潰瘍の場合は、原因となった薬剤の中止が最優先です。中止が難しい場合には、酸分泌抑制剤などで治療を行います。
③ 急性胃炎
まずは胃を休息させることが重要です。そのため、消化に優しい食事(おかゆ、うどん、スープ、白身魚、卵など)をゆっくりとよく噛んで摂取することが勧められます。
症状緩和のため、胃酸分泌抑制薬を用いることもあります。吐き気や嘔吐がひどい場合は、水分補給が上手く行えなくなるため、点滴治療を行うこともあります。
急性胃炎の治療においては、原因を取り除くことが最も重要視されています。規則正しい生活をはじめ、刺激物の摂取を避けたり、過労やストレスを減らしたりすることが大切です。ストレスのコントロールは胃の保護に非常に重要とされており、精神的・肉体的ストレスは胃壁を傷つけやすくします。十分な睡眠とリラクゼーション、趣味やスポーツなどを通して、ストレスを上手く解消させましょう。
④ 慢性胃炎
原因であるピロリ菌の除菌が推奨されます。以前はピロリ菌の除菌は胃潰瘍などの一部の病気に限定されていましたが、現在は慢性胃炎に対しても保険適応となっています。除菌療法はプロトンポンプ阻害薬と2種類の抗生物質を組み合わせて1週間内服します。以前はこの治療法で90%以上の成功率でしたが、最近では耐性菌の出現があり除菌成功率がやや下がってきています。除菌に失敗した場合は、薬の種類を変更して二次治療を試みます。 しかし、ピロリ菌の除菌により逆流性食道炎などの悪化が見られることがあるため、ほかの基礎疾患を有している方に対しては注意が必要です。
⑤ 胃がん
胃がんの治療には「内視鏡的治療」、「外科手術」、「化学療法(抗がん剤治療)」など、がんの進行の程度に応じたさまざまな方法があります。
早期胃がんの段階で診断することができれば、多くが内視鏡的治療で完治します。
かつて胃がんは、日本で最も死亡率の高いがんでしたが、早期発見・早期治療により、死亡率は減少しています。特に、早期のがんならば、90%以上が完治可能と言われています。気になる症状があるときは、早めに当クリニックを受診し、詳細な検査を受け、適切な治療を始めることが大切です。